1 はじめに
こんにちは、弁護士のRayです。当ブログにお立ち寄りいただきありがとうございます。
当ブログでは、弁護士の業務内容の紹介等も随時行っていければと思っております。そこで、今回は、そもそもどうすれば弁護士になることができるのかという点から順番にご紹介することにしました。
2 司法試験
(1) 司法試験の内容
「弁護士」と聞いたら、まず「司法試験」を連想する方が多いのではないでしょうか?実際もそのとおりでして、弁護士になるには司法試験に合格する必要があります。
司法試験は、現在、短答式試験(いわゆるマークシート方式)と論文式試験に分かれています。かつて行われていた口述試験は行われなくなりました。
試験自体は、毎年5月中旬に、間に1日休みを挟んで短答式試験と論文式試験が計4日間の日程で行われています。
短答式試験は、憲法、民法、及び刑法の3科目が実施され、論文式試験は、憲法、民法、刑法に加え、会社法(商法含む)、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法、及び選択科目(労働法、経済法倒産法、倒産法、知的財産法、国際関係法(私法系)、租税法、環境法、国際関係法(公法系)から1科目を選択)の計7科目が実施されます。
司法試験の酷なところは、論文式試験について、公法系(憲法・行政法)2時間×2、民事系(民法・会社法・民事訴訟法)2時間×3、刑事系(刑法・刑事訴訟法)2時間×2、選択科目3時間×1の計17時間必死に論文の答案を作成しても、短答式試験に合格した受験者しか論文式試験の採点をしてもらえない点です。短答式試験に合格しなければ論文式試験が受験できないというのではなく、論文式試験を受験するにもかかわらず採点してもらえないという意味です。この点は受験生に評判が悪い点と言えるでしょう。
(2) 司法試験の受験資格
かつての司法試験(いわゆる旧司法試験)は、大卒者等の1次試験が免除されるなどの取り扱いはありましたが、受験資格はなく、誰でも受験することができました。
ところが、現行の司法試験では、原則として法科大学院を卒業した者しか受験資格を得られないとされています。例外として、別記事で説明予定の予備試験を受験し合格した者も受験資格を与えられます。
もう一つ、旧司法試験と異なる点は、その受験資格に制限期間があり、受験資格を取得した日から最初の4月1日から5年間しか受験資格が認められない点です。
つまり、たとえば平成31年3月に法科大学院を卒業した人は、令和元年5月、令和2年5月、令和3年5月、令和4年5月、及び令和5年5月(令和と書きたいだけとの突っ込みはご容赦ください笑。)に実施されるいずれの司法試験にも合格できなかった場合は、司法試験の受験資格を喪失することになります。
この受験資格喪失制度は、旧司法試験制度下において、受験資格の制限を設けていなかったことから、司法試験浪人生が大量に発生し、多くの若者の人生を狂わせた(とされている)反省から、国が後見的に受験期間に制限を定め、合格する見込みがないものに早期の司法試験からの撤退を促し、まだ軌道修正の効くタイミングで進路変更を強制するという趣旨で設けられました。この制度のお陰で救われた人もいるでしょうし、どうしても法曹(弁護士だけでなく、裁判官、検察官を含める呼び方です。)になりたい人にとっては余計なお世話ということになります。こちらは、賛否両論のある制度となっております。
もっとも、再度法科大学院を卒業したり、予備試験に合格すれば、再度受験資格が与えられます。そのため、現実に2つの法科大学院を卒業し弁護士になった人も存在します。
(3) 司法試験の合格者数・合格率
現在の司法試験制度になってからも、合格者数について変動はありましたが、平成30年以降は、合格者数を1,500名程度にすることが政策として決定されています。現に、平成30年の合格者数は1,525名でした。平成30年の対出願者合格率は、26,24%、対受験者合格率は29,11%でした。
司法試験と聞いて、旧司法試験をイメージされる方は宝くじ級の合格率を想像されるた方も多いかもしれません。しかし、 現在の司法試験は、ある程度高い合格率を維持しております。
ただし、この合格率が司法試験受験資格を保有した者の中の合格率であることを忘れてはなりません。旧司法試験は誰でも受験できていたことを考えれば、旧司法試験の合格率が数%だったとしても、その数字分だけ簡単になったとは言えないでしょう。
とはいえ、旧司法試験から比べてハードルが低くなったことは確かですので、司法試験を狙うのであれば今がおすすめのタイミングだと思います。ぜひ、チャレンジされてみてはいかがでしょう?
3 まとめ
司法試験についてのとりあえずの説明は以上となりますが、司法試験を受験するためのルートである法科大学院、予備試験、また、司法試験合格後に終了しなければならない司法修習については別の機会に書かせていただきます。
最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
4 おまけ(今回の投稿でチャレンジしたこと)
当ブログの一つの目的であるRayのITリテラシー向上の一環として、チャレンジしたことがあれば、報告させいただきたいと考えております。
今回チャレンジした点は、①目次が作成される設定に変更したこと、②①のためにタグを活用したこと、③読者の方が読みやすいようにマーカーを使用したことです。
これからも色々と新しいことを学んでいけたらと思います。
改めまして、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
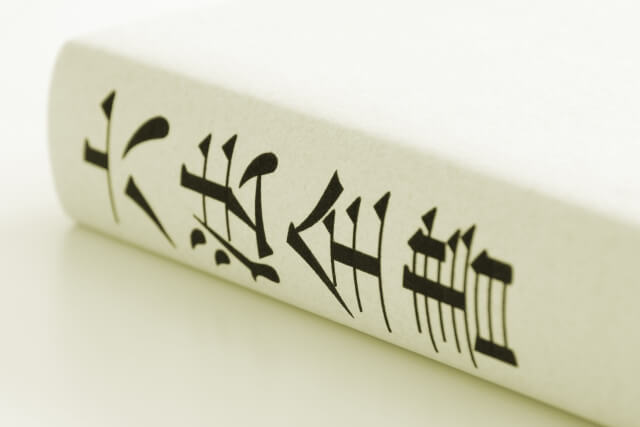


コメント