1 はじめに
これまで、司法試験、法科大学院(ロースクール)について投稿してきました。今回は、司法試験を受験するために、法科大学院を経由くてもよくなるバイパスとなっている予備試験について説明します。
なお、私が法科大学院に在学していたときはまだ予備試験が始まっていないかったことから具体的な経験談として語ることはできないのですが、周囲にいる予備試験合格者の話や我々の業界内で語られていることを中心に述べていきます。そのため、司法試験や法科大学院について述べた投稿よりも具体性に乏しい内容になっていると思いますが、あしからずご了承くださいませ。
2 予備試験って何?
(1) 試験の内容 司法試験とはどう違う?
ア 予備試験の趣旨
そもそも、予備試験とは、平成23年から開始された法科大学院を卒業せずとも司法試験受験資格を得られる試験です。
予備試験制度が開始した趣旨は、法科大学院の学費(国立でも半期40万円超、未修者コースの3年間を前提とすると、入学金含め法科大学院に支払う学費だけで約300万円弱必要となります。)を負担するのが困難な人のために、司法試験の門戸を閉ざしてはならないということで、法科大学院卒業相当の学力があるも者に司法試験受検資格を与えるというものでした。
ところが、現在は上記の目的も全く果たしていないわけではないでしょうが、後に述べる合格率の低さによって、基本的には若手合格者が自らの優秀さをアピールする(箔をつける)手段となっています。要するに、予備試験合格者であるか否かが、法律事務所が新人弁護士を採用する際に応募者の優秀さを測る大きな物差しとなっているということです。大手法律事務所の採用活動において、特に現在は予備試験合格者に優先的に内定を出していると聞いています。
イ 短答式
法科大学院卒業相当の学力を測る試験ですので、その試験内容は基本的には法にかかわるものとなっています。具体的には、短答式では、法律基礎科目として、 憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法 、また、これらに加えて、 一般教養科目として、人文科学、社会科学、自然科学、英語が試験科目となっています。5月中旬ころに実施されます。
ウ 論文式
論文式では、法律基本科目として、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、法律実務基礎科目として、民事訴訟実務、刑事訴訟実務及び法曹倫理、一般教養科目として、人文科学、社会科学、自然科学が試験科目となっております。 短答式合格者を対象に7月頃に実施されます。
エ 口述式
上記は、一般教養科目が加わる点は別として、基本的に司法試験科目と重複する部分が多いのですが、予備試験特有の試験として口述試験というものがあります。 法律実務基礎科目(民事、刑事)について、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかを判定するための試験が行われます。 論文式合格者を対象に10月頃に実施されます。
口述試験まで合格すれば、晴れて司法試験受験資格を得ることになります。具体的には、予備試験合格の翌年から5年間の司法試験を受験する資格が得られます。
オ 予備試験の合格者数・合格率
概ねこれまでの予備試験の結果をまとめると、短答式の合格者2500人前後、合格率20%代前半です。論文式の合格者数は450人前後、合格率は対短答式合格者ベースで20%前後、短答式受験者ベースで4%ほどです。
口述試験の合格者(最終合格者)は450人弱、合格率は対論文式合格者ベースで90%超、短答式受験者ベースで4%弱です。
(2) 予備試験受験のメリット
- 法科大学院の学費がかからない
- 法科大学院での2年3年が短縮できる
- 予備試験は狭き門なのでこれに合格できれば司法試験合格可能性も高く、予備試験合格者の約7割は司法試験に合格する。
- 就職に有利(予備試験合格が採用に有利になる)
(3) 予備試験受験のデメリット
- (予備試験受験者に最も多い大学生という属性を前提に)少なくとも3年生4年生時は予備試験の試験対策に没頭する必要があり、法学部以外の授業・ゼミ・部活・サークル活動・アルバイトに割く時間の確保は困難
- 予備試験の難しさゆえに(法科大学院経由であれば司法試験に合格できたであろう人も)挫折してしまう可能性がある。
- (上位法科大学院では)その分野の第一人者である教授と最先端の議論ができるが、予備試験受験生では難しい。
- ・・・その他は思いつきませんね笑。
3 結局、法科大学院経由とどっちがいいの?
断然予備試験でしょう!
ただし、金銭的事情が許すのであれば、大学卒業と同時に法科大学院に進学できるよう準備をしておくのがベストだと思います。予備試験の準備をまじめにしていれば、上位の法科大学委任に入学することはたやすいと思います。そうすれば、司法試験には合格できるけど予備試験には合格できない状況にある人も、司法試験合格への道を進むことができます。
4 最後に
以上で一通り予備試験について説明しました。今回までで、司法試験合格までの話を説明したことになります。
次は、弁護士・裁判官・検察官になるために必要な司法修習について説明しようと思います。
最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
5 おまけ(今回の投稿でチャレンジしたこと )
次回以降は、チャレンジしたことがあった場合のみ書くようにします。
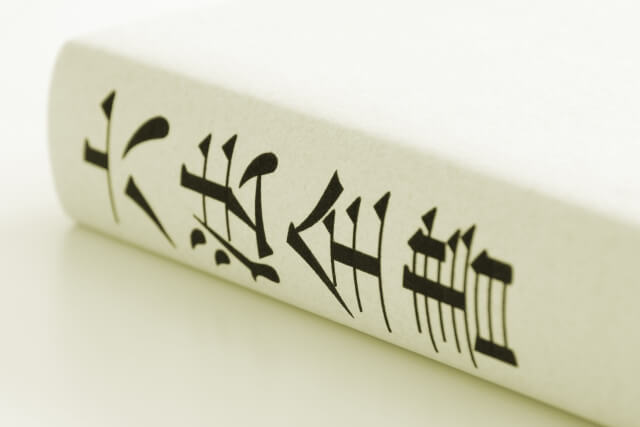

コメント