1 はじめに
こんにちは、弁護士のRayです。当ブログにお立ち寄りいただきありがとうございます。
これまで、弁護士になるために必要なプロセスである司法試験、法科大学院(ロースクール)、予備試験について説明してきました。今回は、その最後のプロセスである司法修習について説明したいと思います。
法曹界にあまり縁のない方にとっては、「司法修習って何?」という感じだったり、テレビドラマ(例えば2003年フジテレビのミムラさん主演の「ビギナー」、2017年日本テレビの福士蒼汰さん主演の「愛してたって、秘密はある。」あたりでしょうか。)で見たことがある程度というイメージしかないのではないでしょうか。
そういった方たちにもよりイメージしていただけるよう分かりやすく説明させていただきます。
2 司法修習とは?
(1) 概要
原則として、弁護士、裁判官、検察官になるには、司法修習を経なければなりません。「原則として」と書いたのは、一般人にはほとんど縁のない例外ルートがあるからです。ここでは、大多数の人にとって意味がないルートなので無視します。
そして、司法修習を受けるには司法試験に合格しなければなりません、という関係になります。
さらに言えば、これまでの記事の繰り返しになりますが、司法試験を受験するためには法科大学院(ロースクール)を卒業するか予備試験に合格しなければなりません。法科大学院(ロースクールに)に入学するためには大卒資格が必要である一方、予備試験には受験資格はありません。
流れとしては、毎年司法試験の合格発表日の1週間余りのち締め切り(9月半ば)で司法修習生の募集がなされます。司法試験合格年の司法試験に申し込む場合(これが一般的ですが)戸籍謄本や健康診断票、大学・法科大学院の成績を提出しないといけないので、バタバタと準備することになります。
無事に申し込みが受け付けられれば、司法修習生に任命され最高裁判所所属の身分となります。 12月頃から司法修習が始まるのですが、その前に事前課題と教科書類が段ボールで送られてきます笑。裁判官になりたい人は 、司法試験の成績に加え、事前課題の出来もみられるのでしっかり取り組む必要があります。 いや、弁護士・検察官になりたい人もしっかりやりましょう!ただ、司法修習の実質は、裁判官・検察官のリクルートにあると言われているのも事実です。
申し込みの際に、配属庁の希望を書くわけですが、最大第6希望まで書くことができるところ、希望の配属庁に配属されるか否かで修習へのモチベーションが大きく変わることでしょう。就職活動の便宜からやはり東京は人気です。また、司法修習前に内定を得ている層からは那覇が一番人気です。
配属庁も決まり、事前課題の提出も終え、晴れて司法修習本番を向かえることになります。 司法修習では、司法試験で特に鍛えていた法的知識の向上はもちろんのこと、事実認定力(証拠からどのような事実を認定するか)をはじめ実務に必要な能力の向上を図ることになります。
基本的な流れは、①導入修習(約一か月@和光)、②分野別実務修習(刑事裁判、弁護、検察、民事裁判各2か月の計8か月@配庁地)、③集合修習(約二か月@和光)、④選択修習(約二か月@プログラムによる)、⑤二回試験(卒業試験)となります。なお、配属庁によっては、③と④の順が逆になります。
現在の制度では、毎月修習給付金13.5万円が支給され、条件を満たせばこれに住宅給付金3.5万円が加算されることになります。これがさらに改悪されることはないでしょうが、現在喧々諤々の議論がされているところですので、業界内では注目を集めているところです。
では、具体的に中身を見ていきましょう!
(2) 導入修習(集合修習@和光)
まず、一ヶ月の導入修習が行われます。
埼玉県和光市の司法研修所に司法修習生が集められ、法的分析能力及び事実認定能力を固めるために、架空の事件記録をもとに、弁護士科目では訴状や弁論要旨(刑事裁判の最後に弁護士が被告人の無罪や情状酌量を目的に述べる内容を書面にしたもの)、裁判科目では判決、検察科目では起訴状及び犯人性を論じる書面を作成し、これらの講評を受けたり、実務修習で気をつけるべきことなどの説明を受けたりします。
なお、法曹業界では一般に書面と作成することを「起案」と言いますので、以下「起案」と書くことにします。
基本的に司法修習生は、毎年1500人ほどいることになるはずですが、1500人が一斉に大講義室で講義を受けるということはなく、60名ほどのクラス毎に講義を受けることになります。
各クラスには各科目(刑事裁判、民事裁判、検察、刑事弁護、民事弁護)の教官が一名ずつ担当することになります。教官によっては、複数のクラスを担当することもあると聞いています。
基本的に各教官は東京を拠点としているので、司法研修生が地方に散らばる分野別実務修習中は、なかなか会えないので、導入修習の際に懇親を深めるべく飲み会や面談が設定されることが多いですので、学生の時と比べれば予定がパンパンになるという人が多いのではないょうか。
ただ、教官は出張で担当司法研修生の配属地に来ることも多ですし、分野別実務修習中に担当教官の講義のスケジュールが組まれることもありますので、分野別実務修習中にクラス担当教官に全く会えないということもありません。
このように、実務の基礎の基礎を学び、クラスを中心に司法修習生同士の関係を育てつつ、分野別実務修習に出ることになります。
(3) 分野別実務修習
分野別実務修習では、1クール約二ヶ月のスケジュールで①刑事裁判修習、②弁護修習、③検察修習、④民事裁判修習を受けることになります。この順は私が経験した順ですが、皆さん、①〜④のどこから始まるかは別にして、順番としてはこのような順番になるはずです。
ア 刑事裁判修習
刑事裁判修習では、裁判所の刑事部に配属になり、部総括判事、右陪席、左陪席の3名の裁判官の下で修習することになります。配属庁にもよると思いますが、私の配属庁では、各部、つまり刑事○部にそれぞれ4名の修習生が配属されるのが通常です。私は刑事裁判修習が最初の実務修習だったので、同じ部に配属された修習生とは特に仲が良いです。
刑事裁判修習で何をするかというと、①傍聴、②起案、③模擬裁判、④他部修習、⑤教官の出張講義くらいでしょうか。
①傍聴ですが、裁判官に伴われて裁判官用通路をとおり法廷に向かい、司法修習生席で裁判を棒傍聴することになります。裁判官室への行き帰りなどで裁判官と事件について、心証はどうだとかあの弁護人はどうだとか議論します。
②起案については、各部の部総括判事のやり方にもよると思いますが、私の部の部総括は、修習生の起案に使えそうな(有罪無罪等の判断が分かれうる)事件の記録をストックしておいてくれ、各修習生に記録を与えて判決を起案させるというやり方でした。私は、強姦殺人の記録でしたが、被害者の証言の信用性の判断に苦慮した記憶があります。的確な講評も受けられ、大変勉強になりました。
③模擬裁判については、同部配属の修習生がそれぞれ、裁判官、検察官、弁護人に分かれて模擬裁判を行うというものでした。私の配属部では模擬裁判の本番は午後いっぱい時間をとってのかなりしっかりしたプログラムとなっていました。
④他部修習については、東京・大阪等の大規模庁でしかないのかもしれませんが、特定の犯罪類型のみを専門的に取り扱う部があるので、その部に一日だけお世話になるというプログラムでした。私は交通事故を扱う部にお世話になりました。
⑤教官の出張講義については、各クールに一回くらいのペースで行われていたように思います。内容は起案と講評ですね。そして、懇親会笑。
今回は、長くなってしまったので、いったんここで終わりにします。司法修習についての説明の残り部分について次回に説明することにし、今回は見出しのみとさせていただきます。
イ 弁護修習
こちらをご参照下さい。
ウ 検察修習
こちらをご参照下さい。
エ 民事裁判修習
こちらをご参照下さい。
(4) 集合修習(集合修習@和光)
こちらをご参照下さい。
(5) 選択修習
こちらをご参照下さい。
(6) 二回試験(卒業試験)
ア 概要
こちらをご参照下さい。
イ 二回試験の合格率はどれくらい?
こちらをご参照下さい。
ウ 二回試験に落ちた場合はどうなるの?
こちらをご参照下さい。
3 さいごに
今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
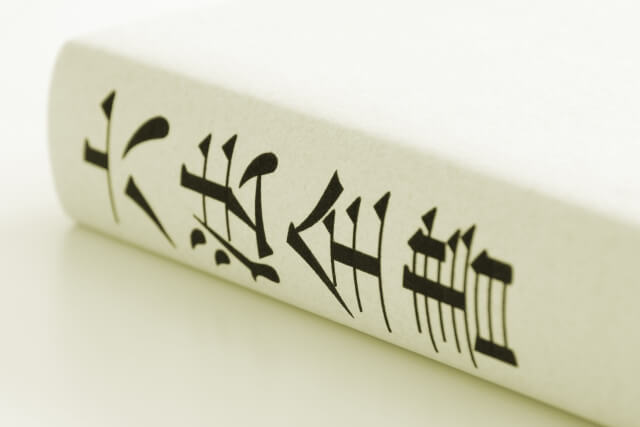

コメント