1 はじめに
こんにちは、弁護士のRayです。当ブログにお立ち寄りいただきありがとうございます。
前回の投稿で途中になってしまった司法修習について、今回は説明の続きを行いたいと思います。
2 分野別実務修習
(1) 刑事裁判修習
前回の投稿をご参照ください。
(2) 弁護修習
弁護修習では、法律事務所に配属され、担当弁護士のもと様々な業務を行うことになります。まだまだ弁護士業界は一人または数人で事務所を運営している弁護士が多いので、基本小規模法律事務所に配属になる修習生が多数だと思います。私も例にもれず小規模法律事務所で修習を行うこととなりました。
弁護修習の内容については、基本的に担当弁護士に始業から就業まで付きっ切りという感じなので、配属される法律事務所によって千差万別とは思いますが、私の経験をもとに大まかに分けると次の通りになりました。すなわち、①民事訴訟対応、②破産申立等その他の裁判手続対応、③顧問先からの相談対応、④国選・当番刑事弁護対応、⑤弁護士会業務対応、⑥教官の出張講義
①民事訴訟対応については、交通事故の損害賠償から契約上の 義務履行請求まで幅広く経験することができました。やはり証人尋問の準備は大変な作業でした。
② 破産申立等その他の裁判手続対応 については、法人・個人の破産申し立てや離婚調停等を経験しました。
③顧問先からの相談対応については、契約書のレビュー、英訳作成等を経験しました。
④国選・当番刑事弁護対応については、当番弁護(逮捕等で身体拘束された被疑者が、無料で弁護士の接見(面会)を受けることができる制度)での接見を一つ経験しました。その後、受任には至らなかったので、担当弁護士は私のために刑事弁護を割と扱っている弁護士に私を里子に出してくださいました笑。そこでは、公判(刑事裁判)も経験することができました。
⑤弁護士会業務対応については、担当弁護士のスタンスにもよりますが私の担当弁護士は会務に積極的だったので、いろいろな会合に同席させていただきました。私は、修習地の弁護士会に登録予定でしたので、ここでの縁が弁護士になった後も生きています。ですので、修習生の皆様には、たとえ担当弁護士が会務に興味のない弁護士だったとしても弁護士会の行事にはできるだけ顔を出すのがよいと思います。私は担当弁護士との相性が大変良かったこともあり、弁護修習は大変良い思い出となっています。
⑥教官の出張講義については、刑事裁判修習と同じで、起案→講評→懇親会ですね。
(3) 検察修習
逆に、私が一番辛かったのは検察修習です。
検察庁では、修習生が大部屋に集められ作業をすることになります。基本的に3人一組で行動することになります。この3人のメンバーは良かったのですが、担当検事との相性はサイアクでしたね笑。
検察修習の内容は、捜査!捜査!捜査!です笑。
先ほど、3人一組で行動すると書きましたが、検察修習では、一人に最低1つの生の事件が与えられ、主任として捜査することになります。同じチームのその他の二人は副担当として主任の修習生をサポートします。ですので、最低主任1件、副担当2件を経験することになります。
修習生とは生の事件を扱うので、警察から送致されてきた本当の事件を取り扱います。警察から送られてきた捜査資料を精査し、起訴するか否かを判断するに足りていない証拠等がないかを確認し、不足している資料があれば警察に指示を出し、補充捜査をしてもらいます。自ら補充捜査をすることもあります。
そして、一番緊張するのが被疑者取調べです。主任の修習生が取り調べを行い、副担当の修習らで記録を取ります。黙秘権の告知から本人確認の質問、事件の詳細について聞いていきます。被疑者の方もこちらが本当の検察官ではなく修習生であることを知っているので、前科〇犯のベテランさんなどは修習生になめた態度をとる人も多いと聞きます。修習生はなめられなように取り調べをしたいところですが中々うまくいかず、私の同チームの修習生が主任でやった案件では完全黙秘をされたりもしました。手を変え品を変え取り調べをなんとか終わらせ調書を完成させます。
捜査が完了したら、担当検事に起訴不起訴の判断及び理由を報告し、決裁をもらいます。ここで簡単に決裁をもらえず検事の部屋と修習生の部屋を何往復もする修習生も多いです。私もそのうちの一人でした。。。
担当検事の決裁をもらうと次は副部長決裁をもらいます。ここでつまずく修習生も多いです。担当検事と副部長の言ってることが違って戸惑う修習生もいました。私もそのうちの一人でした。。。
副部長決裁をもらったら最後に部長の決裁をもらいます。副部長決裁までもらっている段階なので、ここてつまずく人は少ないように思います。
検察官志望の修習生は猛スピードで案件の決裁をもらい、2件目3件目と主任事件をこなすことになります。幸い私のグループに検察官志望はいなかったので一人一件ずつで検察修習は終わりました。
おまけ的に書くと、日々の案件対応以外にも希望者には検視を見学する機会など検察ならではのイベントに参加することもできます。
(4) 民事裁判修習
民事裁判修習は、構成は基本的に刑事裁判修習と同じで、傍聴、起案の繰り返しでしたね。
ただ、民事裁判修習の特徴としては、刑事裁判と違って、ブロックダイヤグラムをたくさん作った点が挙げられると思います。
ブロックダイヤグラムとは、簡単に言うと、原告の主張と被告の反論について、法律上の要件(条件)に従って対立構造を図にまとめることをいいます。司法修習の観点からは、民事裁判のみならず民事弁護科目においても重要な基本スキルとなりますので、数をこなせたことはかなりのトレーニングになったと思います。(もし、リクエストがあればブロックダイヤグラムについての記事も書いてみたいと思います。)
3 集合修習(@和光)
後に説明する選択修習と集合修習は配属庁によって順番が異なります。とりあえず、私が経験したとおりの順番(集合修習→選択修習)で説明することにします。
集合修習では、司法修習の最後に待ち構えている通称二回試験と呼ばれる卒業試験を意識した、起案が繰り返されます。各科目毎に2回はフル起案をしたと思います。そして、あとは講評、細々した講義、クラス総出で行う模擬裁判の準備ですね。
ほとんどそれだけで時間が過ぎていった記憶です。
あとは、基本みんな同じ寮で生活しているので、修習生同士の親睦を深められたのが良かったですね。
もう一つ、記憶に残っているのは裁判官希望の人たちが大変そうだったことです。裁判官に任官されるためには、クラスの裁判官教官の覚えが良くなければならずそのためには司法修習期間中の起案で良い成績を取り続ける必要があるのです。弁護士や検察官希望の修習生が、講義を終えた後寮に付設されている体育館でバレーボールなどでリフレッシュしているときも自室にこもって勉強をしている裁判官希望の修習生の姿は少し気の毒でした。
4 選択修習
選択修習とは、特定のカリキュラムを与えられるのではなく、様々なプログラムから自分好みのプログラムを選択、または自らプログラムを作成(自己開拓プログラム)し、2か月の期間を過ごすというものになります。特段プログラムを入れない期間は、ホームグラウンド修習とされ、弁護修習を行った法律事務所で修習を行うことになります。一般的に、ホームグラウンド修習では、担当弁護士が気を利かせ、基本的には二回試験の勉強を自由にさせてくれることが多いと聞きます(私もそうでした。)。
さて、どのようなプログラムがあるのかという点ですが、まず、自己開拓プログラムはまさに、所与のプログラムではなく修習生自身が企画提案し司法研修所から承認を得て行うものですので、修習生本人の自由裁量に委ねられています。私自身、自己開拓プログラムは行いませんでしたが、同期の弁護士の中には、興味のある企業に直談判し、2週間程度席を置いてもらいビジネスを勉強させてもらったという人もいました。
次に、自己開拓プログラム以外のいわゆる所与のプログラムについては、全国プログラムと配属庁のプログラムに分かれており、全国プログラムはどの配属庁の修習生も応募できるプログラムで、一方配属庁のプログラムは当該配属庁の修習生のみが応募できるプログラムということになります。
全国プログラムには、例えば、JICA(国際協力機構)や法務省での修習、大規模法律事務所修習、渉外弁護修習等がありました。もちろん、定員があるので希望が必ず通るというわけではありませんが魅力的なプログラムが多かったと思います。補足説明をすると、JICAでの修習では途上国の法整備支援について学ぶ機会を与えられ、大規模法律事務所修習では、通常の弁護修習では経験できないような最先端のビジネスローヤーの活動を間近で学ぶことができ、渉外弁護修習では、国境を超えるインターナショナルなビジネスにかかわる弁護士の活動を間近で学ぶことができます。
配属庁のプログラムには、他の配属庁であったものも含めて面白そうなものをほんの一部例示すると、スリ捜査同行、痴漢捜査同行、飲酒運転修習(教習所内のコースで飲酒運転を経験するという内容)、裁判所の専門部修習(商事部、倒産部等)などがありました。
5 二回試験(卒業試験)
(1) 概要
以上の修習をすべて終えると、11月にいわゆる二回試験と呼ばれる卒業試験が行われます。二回試験に合格することが司法修習終了の条件となっているので、弁護士、裁判官、検察官になるには、この試験に合格する必要があります。
それでは、どんな試験なのか概要を見ていきましょう。
民事裁判、刑事裁判、民事弁護、刑事弁護、検察の計5科目につき、1日1科目、1科目10時20分から17時50分の7.5時間(昼食時間1時間含む)で行われます。
昼食時間含む??となった方も多いと思います。要するに、12時から13時の一時間は昼食をとることができるがその時間を試験に使うこともできるという意味です。なので、やる気のある修習生は、おにぎりなど簡単に食べられるものを用意し、数分で昼食を終え試験中断の時間を最小限にとどめる工夫をしています。
あと、そもそも試験時間が長いです。長いですが、凡人には1分たりとも無駄にできる時間はありません。
基本的にすべての科目で、架空の事件記録100ページ超を読み込み、判決なり、訴状なりを起案することになります。
圧倒的な作業量が求められます。疲れます。ですので、冗談抜きで、司法試験はもう一度受けてもいいけど二回試験は・・・という弁護士も多いです。
(2) 二回試験の合格率はどれくらい?
とはいえ、合格率自体は低くなく約95%以上合格します。大体各クラス(60名程度)で2,3人不合格者が出るか出ないかくらいのイメージです。
晴れて二回試験に合格すれば、弁護士、裁判官、検察官になることができます。
一方、合格率が高いため、逆に落ちた時のダメージは大きいです。
(3) 二回試験に落ちたらどうなるの?
二回試験に不合格になると、弁護士、裁判官、検察官にはなれないので、通常、内定をもらっていた法律事務所からは内定を取り消されます。例外的に、事務所のボスから1年待ってもらえる例もあると聞いていますが、これはよほど熱望されている方に限られます。基本内定は取り消されます。裁判官、検察官も基本的には同じです。
手続上のことを説明しますと、二回試験不合格後、司法修習生を罷免されます。そして、当該不合格者の申し出により、翌年の二回試験の直前に再度司法修習生に任命され、翌年の二回試験を受験することになります。
不合格者は、一年間、孤独に勉強する必要がありますが、一応不合格者のネットワークもあり定期的な勉強会や教官からのフォローもあると聞いておりますので、不合格になったとしても絶望せず情報収集はしておいた方が良いと思います。
6 さいごに
以上で、弁護士になるために必要なプロセスをざっくりと説明しました。皆様からのリクエストや私の気分に応じて、もっと深堀りするところも出てくると思いますが、とりあえず「弁護士になるには」編は完了です。
今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
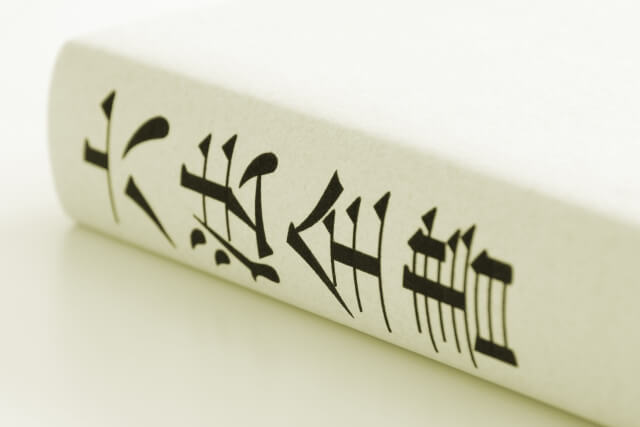


コメント