1 はじめに
こんにちは、弁護士のRayです。当ブログにお立ち寄りいただきありがとうございます。
先日(2019年4月9日)の投稿「弁護士になるには その1(司法試験とは)」に続いて今回も弁護士になるために必要な事項について説明したいと思います。先日は司法試験について説明しましたが、少し復習しましょう。
現在、司法試験の受験資格を得るには、①法科大学院(ロースクール)の卒業(主たるルート)または②予備試験への合格が必要とされています。なお、法科大学院(ロースクール)について、以下では単に法科大学院と記載することにします。
そこで、今回は法科大学院制度および修了者の視点から法科大学院のリアルについて紹介できればと考えております。
2 法科大学院制度
(1) 法科大学院とは?
法科大学院とは、法曹(裁判官・検察官・弁護士)の養成を目的とする専門職大学院です。
この説明だけだと、「専門職大学院って何?」となりますよね?
専門職大学院とは、「大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするもの」(学校教育法第99条第2項)と定義されています。
これでもまだ分かったような分からないような状態だいと思いますので、もう少し補足しますと、皆さんが一般的にイメージされる大学院は、いわゆる学者になるためや(一般就職をするにしても)学問の専門性を高めるために進学するものだと思います。このような、大学院は研究職大学院と呼ばれています。
そして、専門職大学院は、研究職大学院との対比で感がると分かりやすいと思います。
つまり、 専門職大学院とは、アカデミックな研究者ではなく、バリバリ社会の中で実務家として活躍する人材を育成するための教育機関と説明できると思います。
なお、晴れて法科大学院を卒業すると法務博士という学位が与えられます。本当に使い道が分からないのですが。。。
(2) 既修者コースと未修者コースって何?
また、法科大学院には、既修者コース(2年で修了、一定程度の法律の素養がある前提のコース)と未修者コース(3年で修了、法律を学んだことがない人にも対応したコース)の2コースが設置されています。
既修者コースと未修者コースのどちらが原則かという興味深い論点もあるのですが、弁護士になるためには特に関係ないポイントですので軽く触れるに留めておきます。
そもそも、法科大学院制度が設けられた趣旨は、旧司法試験時代における司法浪人の問題を解消するとともに、法曹界に多種多様な人材を受け入れ、より国民にとって身近で利用しやすい司法制度を実現する点にありました。
この法科大学院設立の趣旨からすれば、原則は法学部以外出身者に間口を広げた未修者コースが原則的コースという理解になります。理念としてはそうだと思います。そのため、法科大学院設立元年の2004年、主な法科大学院のうち、早稲田大学・大阪大学などは、定員数の割り振りで未修者の定員を多くしていました。
ところが、わずか3年の勉強期間で司法試験に合格できる未修者コース学生が少なかったため、それらの法科大学院の司法試験合格率は、本来の大学の受験難易度に比してかなり低くなってしまったのです。そうすると、(理念に忠実に法科大学院を運営しているだけなのに?)合格率の低い法科大学院だとレッテルを貼られてしまい、志願者が減少するという負のスパイラルに陥ってしまったのでした。
そこで、早稲田大学・大阪大学などの法科大学院も現在では既修者コースの定員数を多くするようになっています。
理念よりも実利を取らざるを得ないというのが法科大学院の現状です。
(3) 法科大学院にはどうやったら入学できる?
ア 既修者コース
次に、どうやったら、法科大学院に入学できるの?という点について説明します。
一言でいえば、入学したい法科大学院の入学試験に合格する必要があります。そして、法科大学院の入学試験の受験資格は、大学卒業(見込みも含む)です。
それでは、どのような試験が行われるか見ていきます。
- 適性試験:大学受験でいうところセンター試験的な位置づけの試験です。かつては、法科大学院受験者は必ず受験する必要のある試験だったのですが、今は任意受験となっております。一部、適性試験の成績の提出を必須とする法科大学院もあるかもしれないので、受験したい法科大学院のHPを見て、適性試験の要否を必ず確認しておいてください。内容は、就活をしたことのある人にとってみればおなじみのSPIのような試験で、論理的思考力・事務処理能力を測るものとなっています。
- 法律の短答試験(一部):既修者コースは、法律の素養のある者を対象としたコースですので、法律の力が試されます。ただ、筆記試験に加えて短答試験を課すのは一部の法科大学院に限られています。こちらも志望する法科大学院のHPを確認するようにしてください。
- 法律の筆記試験:筆記試験はいずれの法科大学院でも課されます。ただ、試験科目は法科大学院によって変わりますので、 志望する法科大学院のHPを確認するようにしてください。
- 面接(一部):一部の法科大学院では、法曹の適性を見るため、面接試験を課す法科大学院もあります。なぜ、法曹になりたいのか、どんな放送になりたいのか、なぜ当法科大学院を志望するのかといった質問に加えて、法律知識や論理的思考力を問うケース問題を課される形式もあります。こちらも志望する法科大学院の過去問等でどのような形式の面接が行われるのか確認する必要があります。
- その他考慮要:上記以外には、①学部成績、②英語力、③志望理由書(ステートメント)等が考慮されるのが一般的ですが、その比重は各法科大学院によってことなるので、HP等で確認する必要があるでしょう。
イ 未修者コース
基本的に、未修者コースの試験は、既修者コースの法律の試験が、法律の知識を問わない、小論文形式に変わるだけで内容はほとんど変わりません。
ただし、既修者に比べて、法律試験という明確な指標がない分、志望理由、学部成績、適性試験の成績等が重視される傾向があるように思います。また、未修者コースについても各法科大学院ごとに重視するポイントが異なるのでHPの確認は必須です。
(4) 目指すべき法科大学院と入ってはいけない法科大学院
ア 目指すべき法科大学院
司法試験合格者数に比して、あまりに多くの法科大学院が設立されてしまい、合格率が当初の想定されていた70%を大幅に下回り、20%前後で推移してしまっていた結果や、予備試験制度という法科大学院を経由しなくても司法試験を受験できるルートができた影響を受け、法科大学院自体の人気が低落し法科大学院と取り巻く環境は年々厳しくなってきています。
世間一般では名門とされるあの青山学院大学の法科大学院でさえ2018年以降の入学者の募集停止をせざるを得ず、在学生がいなくなった段階で閉校することが決まっています。
そこで、法科大学院への入学を考えている方は、どの法科大学院に入学するか慎重に検討する必要があります。
法科大学院選びの基準としては、
- 大学自体の難易度(大学受験の偏差値)
- 司法試験の合格率
- 著名な教授が多くいるか
- 司法試験委員を務めている教授がどれほどいるか
あたりが重要となってくるのではないでしょうか。法科大学院制度が開始してから10年以上が経過し、法科大学院の実績(司法試験合格率)も大学受験時の偏差値の序列とおおむね同じ形になってきております。そして、有名大学には著名な教授、司法試験委員を務める教授がおり、質の高い講義を受講できるという好循環が生まれており、今後法科大学院の序列が大きく変わることはないものと予想されます。
イ 入ってはいけない法科大学院
逆に、入学すべきでないのは上記要素が芳しくない法科大学院にしか合格できなかった場合です。そもそも、人気の高く競争率の高い法科大学院に入学できないということは、自身が司法試験に向いていないことを示唆する事実とも言えます。そうであるにもかかわらず、いわゆる一般就職の新卒カードを捨ててまで司法の道を目指すのかは一考の余地があると言えそうです。
いったん、新卒で一般企業に就職し、3年間ほど働いてみてそれでも司法の道への未練が断ちきれないようでしたら、その時点で法科大学院に入学する、あるいは、仕事をしながら予備試験を目指すという方法も良いと思います。
社会人経験者(一定程度以上の有名企業での職務経験や特殊スキルを身につけている方)は、法律事務所への就職の観点からも間違いなく有利でして、大手法律事務所から個人法律事務所まで多くの法律事務所が社会人経験者を採用しています。
学部卒でいわゆる中位以下の法科大学院に進学するくらいなら、一度就職し、法科大学院ないし予備試験を経由してから有力な法律事務所に就職する方が良いという考えも十分に成り立ちます。それくらい社会人経験者は法律事務所への就職で強いです。
今回は、長くなってしまったので、法科大学院のリアルについては次回に説明することにし、今回は見出しのみとさせていただきます。
3 法科大学院のリアル
(1) 講義はどんな感じ?
こちらをご参照ください。
(2) 人間関係は?
こちらをご参照ください。
(3) 結局、法科大学院に入って良かったの?
こちらをご参照ください。
4 おまけ (今回の投稿でチャレンジしたこと)
最後に、定番の(?)今回の投稿でチャレンジした点について記録しておきます。
- 当ブログ内の関連記事へのリンクを貼った
- 箇条書き機能を使った
- 強調表現として太文字を使用した
今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。引き続きどうぞよろしくいお願い申し上げます。
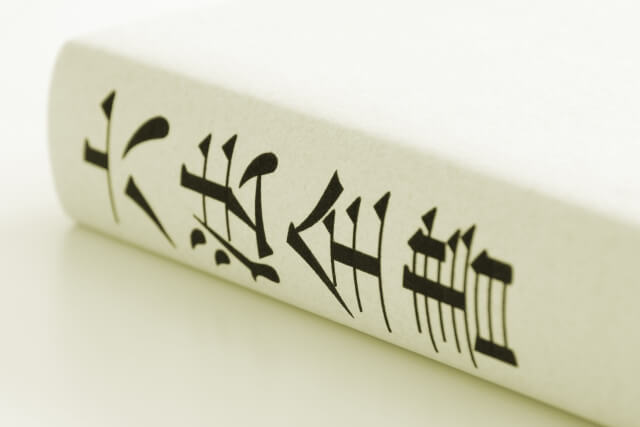

コメント