- 1 はじめに
- 2 やるべきことは12個!!
- 3 やるべき具体的内容!
- ① 司法試験の制度・内容を理解する
- ② 何年何月の司法試験に合格したいかを決める
- ③ どのルートで司法試験受験資格を得るかを決める
- ④ 司法試験合格に必要な総勉強時間を設定する
- ⑤ 1年、1月、1日に確保すべき勉強時間を確認する
- ⑥ 必要な勉強時間を確保できない場合は勉強以外の私生活を調整する、又は、合格目標時期を遅らせる
- ⑦ 基本的知識をどのように身につけるか方法を決める
- ⑧ 法科大学院に進学するならどの法科大学院に進学するかを決める
- ⑨ 予備校を利用するならどの予備校の基礎系講座を受講するか決める
- ⑩ 論文の能力をどのように鍛えるか方法を決める
- ⑪ 予備校を利用するならどの予備校のどの論文系講座を受講するか決める
- ⑫ 合格後の将来をイメージする
- 4 さいごに
1 はじめに
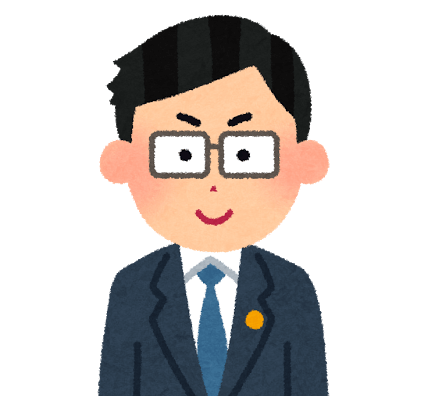
こんにちは、弁護士のRayです。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で2020年実施予定の司法試験・予備試験の延期が決定され、8月に実施されることになりました。
受験生の皆さんはとても不安な気持ちだと思います。ただ、置かれた状況は皆同じですので、厳しいですが、集中力を切らさず本番まで頑張ってほしいと思います。
私に力になれることはそれほどないと思いますが、ご連絡いただければ対応はさせていただきます。
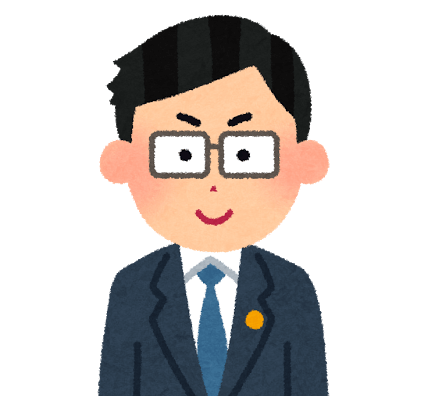
さて、今回は、今年の受験生向けではなく、今まさに司法試験(予備試験・法科大学院)受験を決意された方に向けた記事を書きたいと思います。
司法試験(予備試験・法科大学院ももちろん含みますが、以下では文脈に応じてこれらを「司法試験」と総称することもあります。)を目指すと決めたらまずすべきこと12選ということで、スタートラインで行うべきことをリストアップしていきたいと思います。
膨大な時間をかけて臨む試験になりますから、最初のスタート時点で間違った方向に進んでいってしまうと、とんでもない時間を無駄にしてしまうことになるので、スタート時点が一番重要です!!
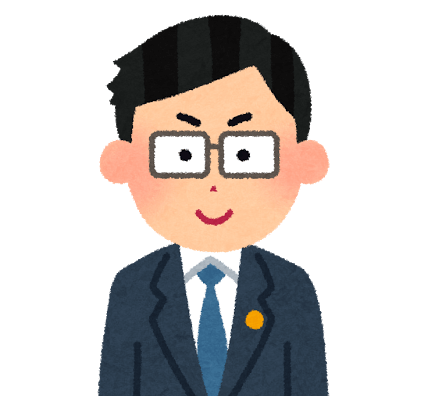
それでは、早速見ていきましょう!!
2 やるべきことは12個!!
やるべきことを以下箇条書きにして示します。
読まなくても分かるよという点はとばしていただき、気になる項目の数字をクリックして該当箇所にジャンプしてもらえればと思います。
① 司法試験の制度・内容を理解する
② 何年何月の司法試験に合格したいかを決める
③ どのルートで司法試験受験資格を得るかを決める
④ 司法試験合格に必要な総勉強時間を設定する
⑤ 1年、1月、1日に確保すべき勉強時間を確認する
⑥ 必要な勉強時間を確保できない場合は勉強以外の私生活を調整する、又は、合格目標時期を遅らせる
⑦ 基本的知識をどのように身につけるか方法を決める
⑧ 法科大学院に進学するならどの法科大学院に進学するかを決める
⑨ 予備校を利用するならどの予備校のどの基礎系講座を受講するか決める
⑩ 論文の能力をどのように鍛えるか方法を決める
⑪ 予備校を利用するならどの予備校のどの論文系講座を受講するか決める
⑫ 合格後の将来をイメージする
3 やるべき具体的内容!
① 司法試験の制度・内容を理解する
試合に勝つにはまず相手を知ることからです!
司法試験に合格するために必要な資格(予備試験や法科大学院制度)についてきちんと調べましょう!このブログでも紹介しているので過去記事もご参照いただけると嬉しいです。
制度だけでなく、試験の内容についてもきちんと調べましょう!どのような科目・内容の試験があるのか、これらの試験によってどのような能力が問われているのかも含めて理解するようにしましょう。
どのような能力が求められているのかを知ることができれば、いわゆる司法試験の勉強をしていないその他の時間でも意識的にその能力を高めることができます。大袈裟な言い方になりますが、24時間勉強している状態に持っていくことも可能です。
試験内容等については過去記事でも触れていますので参考にしてください。
また、求められる能力については、法務省のウェブサイトで毎年の司法試験について出題の趣旨及び採点実感が公表されているのですが、その中で触れられています。例えば昨年の司法試験の出題の趣旨及び採点実感はこちらです。
ただ、法律の勉強を全くしたことのない方がいきなり出題の趣旨や採点時間を読んでもよく分からない部分が多いと思いますので、ある程度勉強を進めるまでは「論理的思考力」と「日本語力」が求められていると理解して進めていただくのが良いと思います。
② 何年何月の司法試験に合格したいかを決める
試験制度を理解したら、目標を設定することが何より重要です。準備期間の長短によって戦略も変わってきますので。
とりあえず、自分自身の希望重視で設定してみることをオススメします。以下の⑫までを検討して難しそうであれば、再検討すればよいだけの話です。
自分の本当の気持ちに素直になるのが大事だと思います。そのためなら頑張れる気がしませんか?
③ どのルートで司法試験受験資格を得るかを決める
予備試験と法科大学院のどちらを経由して受験資格を得るのかを決める必要があります。もちろん、現役大学生などは両にらみで進めるのも合理的だと思います。
どのルートをとるかによって、司法試験前のイベントの時期・完成度が変わってくるので、決めておく必要があります。
大まかなイメージでいうと、予備試験経由の方がコストは低いですが予備試験の合格率が低く勉強はハードになります。法科大学院経由だと、法科大学院の合格自体はハードルが低く、余裕をもって勉強が進められる一方、司法試験合格までの期間がどうしても長くなってしまいます。また、法科大学院の2年又は3年の学費コストが高額となってしまいます。
自分の置かれた状況や目標に合わせてルートを選択してください!
なお、法科大学院についての過去記事や予備試験についての過去記事も参考にしていただければと思います。
④ 司法試験合格に必要な総勉強時間を設定する
司法試験(予備試験含む)合格に必要な勉強時間は、3000時間~10000時間と案内されることが多いです。私自身は法科大学院経由のコースですがざっくり7500時間(法科大学院の司法試験に直接関係のない勉強も含む)程度だったと思います。
このレンジからだいたい自分に必要と思われる時間を予想してみましょう。
留意点としては、(まともに勝負できる)司法試験受験生の平均的レベルは学部早慶卒くらいという点です。ですので、このレベルから自分がどれくらい上なのか又は下なのかを客観的に判断した上で必要な勉強時間を予想しましょう。
⑤ 1年、1月、1日に確保すべき勉強時間を確認する
④で必要な勉強時間、②で本番(司法試験・予備試験・法科大学院)までの残り日数が決まりますので、単純に割るだけです。
ただ、予定通りにいかないこともあるので、バッファーは持たせた方がよいでしょうね。週7日毎日勉強する計画であっても6.5日として計算するくらいは余裕を持たせた方がよいでしょう。
無理なスケジュールであれば修正すれば良いというのはその通りですが、あまりに頻繁に修正すると訳が分からなくなってくるためです。
⑥ 必要な勉強時間を確保できない場合は勉強以外の私生活を調整する、又は、合格目標時期を遅らせる
⑤の計算の結果、1日、1月、1年に必要な勉強時間が確保できない場合は、私生活を調整するか、②に戻って目標合格時期を遅らせることが必要でしょう。
私生活の調整の例としては、サラリーマンを続けながらの受験勉強を考えていたけれどやはり退職(休職・時短勤務等)して目標期限までは受験勉強に専念することにする、アルバイトしながらの受験勉強を考えていたけれど実家に戻ってアルバイトの時間や家事の時間を減らす、子供を親等に預ける日を設けることなどが考えられます。
どうしても調整ができない場合は、目標合格時期を後ろにズラすしかないと思います。
受験生活では犠牲にするものが大きいので、合格できる自信のないスケジュールで進めていってしまうのは極めて危険な行為だと思います。このスケジュールなら合格できると自分で思えることが大事です。自分の合格を信じて勉強するのとそうでないのとでは必ず大きな差になってしまいます。
スタートまでは冷静に、スタートしたら勉強の鬼になるというのが望ましい姿だと思います。
⑦ 基本的知識をどのように身につけるか方法を決める
司法試験を受験するにあたって基本的知識の習得は必要不可欠であり、習得方法としては以下の三つが考えられます。
●独学
●法科大学院の授業に合わせて勉強する
●予備校を利用する
中には法科大学院に通いつつ予備校を利用する方、法科大学院入学前に予備校を利用する方もいると思います。
お金の問題がないのであれば、予備校を利用することをオススメします。特に基礎知識習得の段階では。
もちろん、後で述べるとおり、論述対策の講座もセットで受講できるのであればそれが望ましいですが、金銭面の負担もありますし、どれか一つといえば私は基礎講座を選びます。
資格スクエア、伊藤塾、辰巳法律研究所、LECと有名な予備校はいずれも基礎知識を習得するための基礎系講座を用意しています。なお、基礎系講座とは、憲法、民法、刑法、会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法の基礎について講義形式でインプットを行う講座を意味します。
いきなり学者の書いた基本書を読んでも理解できず挫折する可能性が高く、また、間違った方向で勉強を進めてしまうリスクがある(そうならないために司法試験で求められる能力を意識するのですが)ので、まずは基礎系講座を受講することをオススメします。基礎系講座を受講しきちんと知識を身につければ、学者の基本書に書かれている内容もほとんど理解できるようになります。
資格スクエアでは「基礎講座Ⅰ・Ⅱ」、伊藤塾では「体系マスター」・「基礎マスター」、辰巳法律研究所では「基礎講座」、LECでは「入門講座」とよばれています。
それぞれの料金と時間数については以下にまとめてみました。但し、LECのウェブサイトは見づらく、「入門講座」単体の料金がわからなかったため省略しております。
●資格スクエア…約310時間・37万7300円(税込)(予備試験入門講座10時間分も含む)
●伊藤塾…約486時間・72万1300円(税込)
●辰巳…約309時間・43万3100円(税込)
●LEC…約321時間・金額不明
個人的に私のオススメは資格スクエアの基礎講座です。私の受験生時代お世話になった高野泰衡先生が担当されているからです。高野先生の説明はとても分かりやすいですし、単に丸暗記だけでない世界を教えてくれます(これは基礎を終えて、学者の本を読むときや実務出て仕事をするにあたりとても良い影響を受けていると思います。)。
加えて、話し方・声も良く(渋く)聴きやすくとても続けやすかったです。上記のとおり長期間の講義を主にwebで視聴し続けることになります。その中で話し方が上手で良い声であるというのは外せないポイントだと思います。
各予備校のウェブサイトでサンプル動画が上がっておりますので、見比べてみるのも良いと思います。
⑧ 法科大学院に進学するならどの法科大学院に進学するかを決める
法科大学院の選び方については、過去記事に書いてありますが、司法試験受験生の平均レベルが学部早慶卒程度ですので、早慶以上の法科大学院に進学することをオススメします。
簡単に、一つは、就職活動(法律事務所、裁判官、検察官)において、学歴が悪いとそれだけでマイナスになってしまうこと。この場合学歴が悪いとは早慶未満を指します。通常の大学受験の感覚と異なる点に留意が必要です。
また、法科大学院に進学するメリットとして切磋琢磨する仲間が得られるという点があるのですが、レベルの低い法科大学院に行くと、このメリットが得られず、変な人間関係に巻き込まれたりするリスクや合格レベルを見誤る可能性もあります。
以上を踏まえてなお、事情があっていわゆるレベルの低い法科大学院に進学する場合は良いですが、レベルの低い法科大学院にしか合格できない人は司法試験に向いていない可能性が相当あると思いますので、進学先はよく考えて決めるようにしましょう。
⑨ 予備校を利用するならどの予備校の基礎系講座を受講するか決める
⑦でほとんど述べてしまいましたが、予備校を利用するのであればどの予備校を利用するかを決めましょう。
⑩ 論文の能力をどのように鍛えるか方法を決める
司法試験には大きく短答式試験と論文式試験があり、双方に基本的知識が必要であることは間違いないのですが、論文式試験では、基本的知識に裏打ちされた論述力が求められます。
基本的に、実際に答案を書いて自分や他人からの添削を受けることを繰り返して、論述力を高めていくことになります。
方法としては、以下の4つが考えられます。
●独学
●法科大学院等の教授等に添削を依頼する
●知人とゼミを組む
●予備校を利用する
これらはどれか一つだけというより組み合わせて活用する方が多い印象です(私が法科大学院経由というのもあるでしょうけれど。)。
良い解説が付いている論文トレーニングの本を使えば独学も十分可能です。ただ、自分で自分をチェックする場合、はやり見落としが出てくるリスクもあります。ですので、できれば他の方法も組み合わせることが望ましいと思います。
法科大学院経由でない場合は、学者とコンタクトをとることもハードルが高く、ましてや添削を依頼するなど学部のゼミの担当教授くらいしかできないのではないかと思います。
ですので、法科大学院経由でない方には、経済的に余裕があれば、予備校の利用をオススメしております。基礎系講座よりは低額なのが一般的であり、かつ、基礎講座とセットで申し込めば多少の割引が受けられることが多いです。
ちなみに、基礎系講座と論文講座は同じ予備校を選んだ方が良いと思います。やはり、どの予備校でも基礎系講座と論文講座の連携が意識されていますので、特別の事情がない限り、予備校を変えるのはもったいないです。
⑪ 予備校を利用するならどの予備校のどの論文系講座を受講するか決める
⑩で予備校を利用することにしたならどの予備校の講座を受講するか決める必要がありますね。
⑫ 合格後の将来をイメージする
皆さん、司法試験に合格することが最終的な目標ではないはずです。ほとんどの方は、資格を得て法曹として活躍するために司法試験に臨むはずです。
活躍している自分の姿をイメージしましょう!
このようなイメージを持っていれば、モチベーションを保ちながら、自分の立てた計画を信じ、やり抜くことができるはずです。
4 さいごに
司法試験を目指すことを決めたみなさん!
暗いニュースが多いと思われがちなこの業界ですが、まだまだ捨てたものじゃありません。
時間をかけて目指す価値のある世界だと思います。
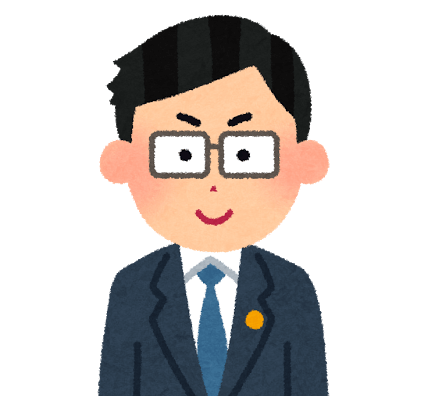
頑張ってください!



コメント