1 はじめに
こんにちは、弁護士のRayです。当ブログにお立ち寄りいただきありがとうございます。
今回は前回の投稿(弁護士になるには その2(法科大学院(ロースクール)のリアルとは①))で時間切れになってしまった法科大学院のリアルについて説明したいと思います。基本的に私の経験と司法修習中などに他の法科大学院出身の同期等に聞いた話も織り交ぜていきたいと思います。そのため、100%の真実である保証は出来かねますので、あくまでイメージとして参考に読んでいただければと思います。もちろん、各法科大学院ごとの特色もあれば学年ごとの特色もあるのでこういった意味でもあくまで一例として理解していただく必要があります。
また、匿名で当ブログを運営していこうと考えていることから、個人の特定につながりうる私の出身法科大学院についても具体名は控えさせていただきたいと思います。
2 法科大学院のリアル
(1) 講義はどんな感じ?
講義については、未修者コースを前提に説明します。既修者コースの講義については2年生以降の部分を読んでいただければと思います。
ア 1年生
1年生の時期は基礎科目を中心に講義を受けます。具体的には、一般的に、憲法(人権・統治)計4単位、民法(総則・物権・債権総則・債権各論)計12単位、刑法(総論・各論)計8単位、会社法計4単位、民事訴訟法計2単位、刑事訴訟法計2単位、行政法計2単位くらいのイメージだと思います。なお、民法の親族相続法は2単位くらいで必修になっている法科大学院と選択科目としている法科大学院に分かれているイメージです。
各科目のどの部分を前期・後期のいずれの学期に配置するかは、法科大学院ごとに異なりますが、基本的にその他の選択科目(リーガルライティング、法哲学、外国法、法と経済等)などと併せて一日2から4コマ受講することになると思います。
司法試験合格が最大の目標なので、司法試験科目である必修科目の勉強を優先することになります。必修科目については、講義一回につき、シラバスで指定されている基本書の該当範囲、該当裁判例を読み込むことが最低限の予習として求められることになります。私の場合、科目にもよりますが、1コマの予習を終わらせるのに4時間程度要していました。科目によっては6時間以上掛かる者もありました。ですので、基本的に、一日の勉強時間は、講義と翌日の予習(約1.5h×3+約4h×3=約16.5h)だけで終わってしまうことがほとんどでした。
要するに復習がおろそかになっていました。これは、ほとんどの未修者に当てはまると思いますう。土日で復習しようと試みたのですが、結局は予習に時間の掛かる科目の予習の予備日となってしまい、特に法律の勉強になれていない前期に復習の時間を確保することは困難でした。
そこで、暗記の多い科目等で、強制的に復習する時間をとるため、クラスの何人かで講義の理解度及び講義の範囲に含まれる基礎知識の定着を目的とした自主ゼミを行っていました。
このように、毎日予習に追われ、睡魔や終電の時間と戦いながら、どこまで深く判例分析を行うか葛藤しながらどこかで折り合いをつけて切り上げて翌日の講義を迎えるということを繰り返すのが1年生の時期だと思います。
2年生になると、クラスが同じになるかは別として、既修者コースで入学してくる司法試験合格を目標とし法学部でみっちり法学を修めてきた人(社会人経由の方とかもいるので全員に当てはまるわけではありません。)と合流するわけですから、彼らに追いついておく必要がある1年生の時が、私だけでなく多くの未修者にとっては一番しんどい時期になるものと思います
イ 2年生
既修者コースの人も入学してきます。未修者組とクラスを混ぜる法科大学院もあれば、卒業まで分離したままの法科大学院もあると聞いています。
基本的に、司法試験科目になる必修科目は 、憲法応用(人権・統治)計2単位、民法応用(総則・物権・債権総則・債権各論)計4単位、刑法(総論・各論)計4単位、会社法応用計2単位、民事訴訟法応用計2単位、刑事訴訟法応用計2単位、行政法応用計2単位 のイメージでしょうか。
その他の必修科目では、法曹倫理(2単位)、要件事実(2単位)、民事・刑事裁判実務(各2単位)くらいがあるのが一般的でしょうか。
選択科目では、各自が司法試験で選択して受験する、 労働法、経済法倒産法、倒産法、知的財産法、国際関係法(私法系)、租税法、環境法、国際関係法(公法系) から最低1科目(卒業単位や実務に就いたときのために複数選択する人は多いです。)選択するのが一般てきでしょう。
その他、法律事務所でのエクスターンシップや、少年事件、金融法、保険法、ベンチャービジネス等様々な科目が開講されるので興味や卒業単位との兼ね合いで選択することになります。
コマ数的には、気持ち1年生時より少なくなるのが一般的ではないでしょうか。
必修科目の講義スタイルも1年時とは異なり、基本的にはケースを与えられ、それに関するレポートを作成し、講義ではその内容について討議を行うというスタイルが増えてきます。ただし、結局該当箇所の基礎知識を確認し、ケースに近い裁判例を分析するという意味では予習に必要な作業は大きく変わりませんでした(つまり、要する時間もです・・・笑)。ただ、法律の勉強になれてきて、自分に知識が増えていることや理解が深まっていることを実感し始める時期でもありましたので、個人的には1年時ほどのつらさはなかったです。
また、ぼちぼち、論文対策の自主ゼミなどが始まる時期でもあります。
ウ 3年生
3年生になると必修科目というのはほとんどなく、基本的に2年生次と同じ選択科目群から興味や卒業単位との兼ね合いで科目を選択することになります。
1年生、2年生でまじめに単位を取得していれば、(卒業に必要な単位+2-4単位にまとめうるならば)1日1コマ程度の時間割になるのが通常ではないでしょうか。
講義の準備等に割く時間が圧倒的に少なくなるのでここで本格的に?司法試験対策に没頭し始めることになります。
予備校の論文講座を受講する人も多いと思います。
(2) 人間関係は?
法科大学院ごとのカラー、学年ごとクラスごとのカラーもあると思いますので、一概には言えませんが、ある程度上位の法科大学院であれば、普通に勉強すれば司法試験に合格できるという心の余裕があるからか、足の引っ張り合いのようなものはなく、むしろ、みんなで協力して効率よく合格しようぜ!みたいな雰囲気になることが多いのではないでしょうか。
逆に、いわゆる下位に分類される法科大学院については、足の引っ張り合いやややこしい人間関係に巻き込まれて集中できないなどといった話を聞いたこともあります。
やはり学生なので、クラス内恋愛はごく普通に存在し誰が誰にフラれたなどといった話が出ることも多いです。かくいう私も・・・笑。
(3) 結局、法科大学院に入って良かったの ?
私は、法科大学院制度がなければ弁護士になろうとは思わなかったので、その意味で法科大学院に入って良かったと思っています。
そして、まさに今現在弁護士や裁判官、検察官になりたいと考えている人には法科大学院入学はおすすめです。法科大学院人気の低迷により定員が激減する一方司法試験合格者数は約1500人を維持する方針がとられているため、法科大学院さえ卒業すれば、受験回数が何回になるかはともかくとして、基本的には皆が合格できるようになっているからです。
ただ、制度の良し悪しについて考えるのであれば、私は、司法制度の現状を踏まえ、法科大学院の存否や役割を真剣に考える必要があると思っています。この点については、別記事でいつか触れたいと思います。
3 さいごに
法科大学院のリアルについての説明は以上となりますが、他にも思い出したことやご質問があれば別の機会に書かせていただきます。
最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
4 おまけ(今回の投稿でチャレンジしたこと)
実は、今回ブログ記事作成で新たにチャレンジしたことはありません。次回、何かチャレンジしたいと思います!
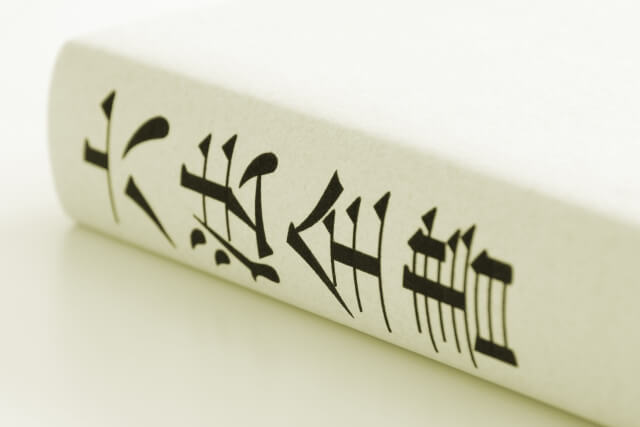

コメント